「絵の勉強を始めたいけれど、何から手をつければいいのかわからない」「上達したいのに、なかなか思うように進まない」そんな悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
独学や専門講座、様々な練習法がある中で、効率良くスキルを伸ばすためには自分に合った方法を知ることが大切です。
本記事では、初心者が最初に取り組むべき絵の勉強内容から、効果的な練習のコツやモチベーション維持法まで徹底解説します。
壁にぶつかった時の対処法や、おすすめの教材も紹介していますので、あなたの「描きたい」を叶えるヒントがきっと見つかります。
自分なりの成長ルートを見つける参考に、ぜひ続きをご覧ください。
絵の勉強を効果的に進める方法
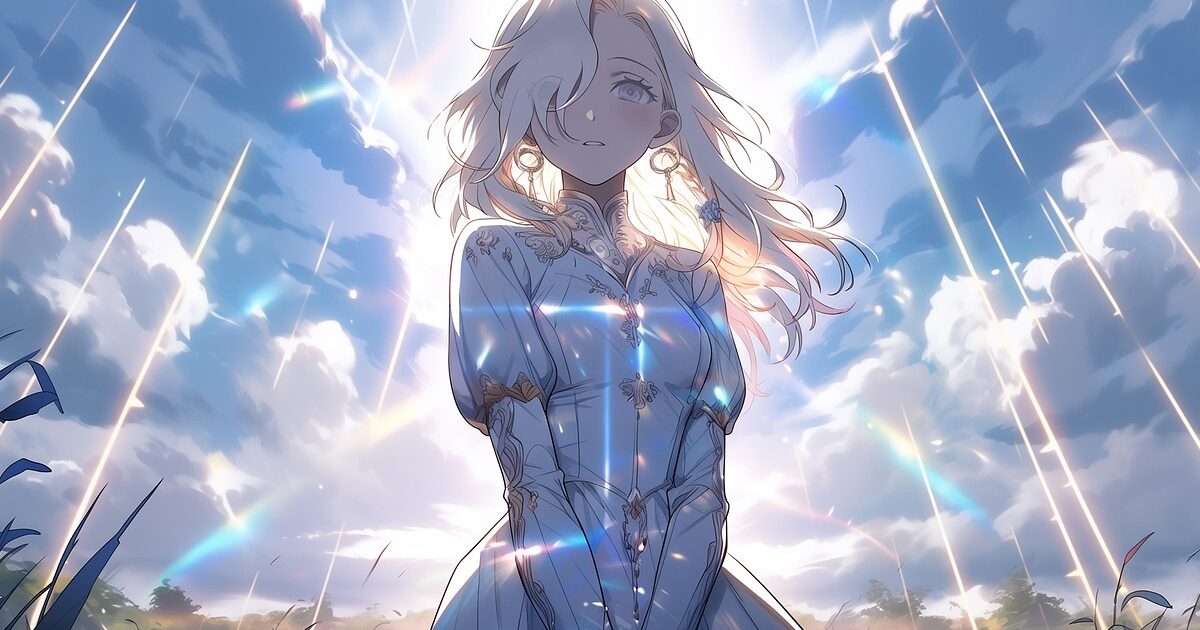
絵の勉強を効率よく進めるためには、ただやみくもに描くだけではなく、段階を意識した練習方法と継続が大切です。
観察力や基礎スキルをバランスよく身に付けることで、着実に上達していきます。
それぞれのコツを押さえて、楽しみながら自分のペースで絵の上達を目指しましょう。
観察力を鍛える練習
絵を描くうえで欠かせないのが観察力です。
身近なものをじっくり観察し、実際の形や質感、光と影の違いを感じ取ることが重要となります。
例えば、同じものを「見る」だけでなく「形を意識して観察」し、細部まで丁寧にスケッチしてみましょう。
観察する際には、単純な形やパーツごとに分けたり、遠近感を意識することもポイントです。
模写とトレースの実施
憧れのイラストや有名な絵画を模写したり、トレースして練習する方法も効果的です。
模写は、描き方や線の流れ、バランス感覚を学ぶ手助けとなります。
トレース練習では、自分の中で感覚を掴みやすく、構図や人体の構造も理解しやすくなります。
- 好きなイラストレーターの作品を選び、手順通りに真似てみる
- 写真をなぞりながら、線の特徴や形を捉える
- 模写とトレースを交互に取り入れ、上達度を比べる
デッサン基礎の習得
形を正確に捉えるデッサンの基礎を身に付けることで、どんな絵にも応用が利くようになります。
デッサンは、立体感やバランス、パースを理解するための基盤づくりです。
まずはシンプルなモチーフから始め、光の当たり方や陰影表現を意識して取り組みましょう。
| 練習素材 | おすすめのポイント |
|---|---|
| リンゴや球体 | 光と影、簡単な立体感が掴みやすい |
| コップや箱 | 直線と角の表現、パースの練習になる |
| 手や顔のパーツ | 難易度は高いが、人体描写の基礎作り |
毎日の練習習慣化
絵の勉強は、短時間でも毎日続けることが理想的です。
毎日描くことで感覚が磨かれ、自然と上達へとつながります。
決まった時間やタイミングを決めて、無理なく続けられるよう工夫しましょう。
一日1枚のスケッチや5分間ドローイングなど、小さな目標を積み重ねることがコツです。
自分の目標や描きたいテーマの明確化
なぜ絵を描きたいのか、どんな作品を作りたいのか、自分の目標やテーマを明確にすることで、やる気が持続しやすくなります。
描きたいものが見つかれば、学ぶべきスキルもはっきりして効率的に練習できます。
イラスト、アニメ、油彩など、ジャンルや作風を決めて取り組むと、目標達成までの道のりも分かりやすくなります。
苦手な分野の重点強化
自分が苦手と感じる分野こそ、意識して練習することが大切です。
苦手な部分に向き合うことで、全体的な画力アップにつながります。
人物、風景、動物など、難しいと感じる対象を絞って集中的に練習してみましょう。
なかなか上手く描けない時でも、続けるうちに徐々にできることが増えていきます。
人に見せてフィードバックを受ける
自分一人で描いていると、どうしても気づけないポイントが出てきます。
家族や友人、SNSなどを活用して、他の人に作品を見てもらいましょう。
客観的な意見やアドバイスをもらうことで、自分では気づかなかった改善点が見つかります。
フィードバックを活かして描き直してみると、新たな発見があるはずです。
初心者が最初に取り組むべき絵の勉強内容

絵の勉強を始めたばかりの方が効率よく上達するには、基礎から段階的に学ぶことが大切です。
ここでは、初心者が最初に取り組むべき絵の勉強内容について具体的に紹介します。
形の捉え方とアタリの練習
まず大切なのは、描こうとするものの形を正しく捉える力を身につけることです。
アタリとは、絵を描き始める際に大まかな位置やバランス、プロポーションを簡単な線や図形で示す作業のことです。
アタリの練習をすることで、全体のバランスを崩さずに描けるようになります。
まずは円や四角、三角といったシンプルな図形から始めて、その後でモチーフの輪郭をアウトラインとして捉えてみましょう。
線画の練習
次に取り組みたいのが線画の練習です。
きれいな線を引くことは、絵に安定感を与えるための基本となります。
いきなり複雑なイラストを描こうとするのではなく、まずは線をまっすぐ引く練習や、同じ長さの線を何本も引く練習から始めてみましょう。
- まっすぐな線を引く
- 曲線やジグザグの線を描く
- 太さや濃さをコントロールしながら描く
手首や肘を使って、リラックスしながら描くことを意識して練習してみてください。
明暗と立体感の理解
絵にリアリティを持たせたり、立体的に見せたりするためには明暗の理解が大切です。
光源がどこにあるのかを考え、その影響を意識してモチーフに明るい部分と暗い部分を描き分けます。
以下の表は、明暗で気を付ける基本ポイントです。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 光源の位置 | 明るい部分と影のでき方が決まる |
| グラデーション | 段階的な明るさの変化を表現する |
| 影の硬さ | 光の強さや距離で影の輪郭が変わる |
明暗を意識することで、同じ線画でも一気に立体感が増して見えるようになります。
簡単なモチーフを使った練習
基礎を体得するには、難しいものをいきなり描くのではなく、日常にある簡単なモチーフから練習するのがおすすめです。
例えば、リンゴやコップ、積み木などのシンプルな形のものは練習に最適です。
これらのモチーフをいろいろな角度から観察し、線や明暗を使って描いてみましょう。
繰り返し描くことで、ものの形を把握する力や、立体感の表現力が徐々に身についていきます。
おすすめの題材選び
初心者におすすめの題材は、自分が興味を持てるものや、身近にあるものです。
描きやすい題材を選ぶと、絵の勉強を続けるモチベーションにも繋がります。
以下のようなものが最初の題材として人気です。
- 果物や野菜
- コップや皿などの食器
- 本や文房具
- 動物や植物の簡単なスケッチ
- 身の回りのお気に入りの小物
最初は上手に描けなくても、楽しみながら継続することが絵の勉強において一番大切です。
絵の勉強におすすめの練習方法

絵の勉強にはいろいろな練習方法があります。
自分の目的やレベルに合わせて取り組むことで、着実にスキルアップにつながります。
初心者から上級者まで、幅広い人に役立つ方法を紹介します。
クロッキー
クロッキーは、短い時間で対象物をサッと描き出す練習方法です。
通常は1分から5分ほどで描くことが多く、線の勢いや全体のバランスを掴むのに役立ちます。
形をしっかり取ろうとするよりも、ざっくりと特徴をとらえることを意識しましょう。
クロッキーを繰り返すことで、観察力やスピード、空間把握力が向上します。
- 人物や動物などのポーズを描く
- 日常の身近なものを描いてみる
- 短時間で集中力を高める
模写
模写はお手本となる絵や写真を見ながら、できるだけ同じように描く練習です。
有名な作品や好きなイラストを模写することで、構図や線の引き方、色の使い方を学べます。
模写するときは、なぜその線や色になっているのかを考えながら描くとより効果的です。
模写を続けることで、自然と自分の引き出しが増えていきます。
| 模写の対象 | 得られる効果 |
|---|---|
| 有名な絵画 | 構図や色彩の理解アップ |
| 好きなイラスト | 線の運びやキャラクター表現の習得 |
| 写真 | リアルな形や質感の把握 |
トレース
トレースは、透明な紙の上にお手本を敷いて線をなぞる練習方法です。
初心者でもすぐに取り組め、形を正確に取るコツや線を丁寧に引く力が身につきます。
なぞった線の動きを何度も繰り返すことで、自然と手が慣れてきます。
ただし、トレースばかりに頼りすぎると自力で描く力が伸びにくいので、他の練習と組み合わせて使うのがおすすめです。
写真や実物の観察
実際に目の前にある物や写真をじっくり観察して描くことで、リアルな表現や説得力のある形が身につきます。
観察するときは、光と影、質感、輪郭だけでなく、全体のバランスを見ることも意識しましょう。
同じモチーフを角度を変えて描いたり、自然光・人工光の違いなどにもチャレンジすると応用力が高まります。
観察力を鍛えることは、どんな絵を描く上でも大切な基礎になります。
テーマ決めドローイング
自分で好きなテーマやお題を決めて自由に描くことで、発想力や表現力が鍛えられます。
例えば「春」「休日のカフェ」「未来の乗り物」など、なんでも自由に決めてOKです。
テーマを決めて描くコツは、最初は簡単なものから始めて、徐々に難易度を上げてみることです。
- 思いついたアイデアを書き出す
- 構図や色を考えながら下描きをする
- 仕上がった絵を見直して改善点を探す
この練習を続けることで、着実に表現の幅が広がります。
デッサン、パース、色彩などの分野別勉強法

絵の勉強では、デッサン、パース、色彩といった各分野ごとに効果的な学び方があります。
目的や現時点のスキルによって取り組み方も異なるため、自分に合った方法を見つけることが大切です。
それぞれの分野で基礎力をしっかり身につけることで、イラストや絵画の表現力が大きく広がります。
ここでは、各分野の具体的な勉強法やポイントを紹介します。
デッサン力向上のステップ
デッサン力を高めるためには、まず正確に「見る力」と「描く力」を鍛えることが基本です。
最初は卵やリンゴなどのシンプルな静物を観察し、その形や陰影、質感を丁寧に描く練習をしましょう。
次に、石膏像や人間の手足といった複雑なモチーフにも挑戦します。
観察する際は、対象の輪郭だけでなく、光と影の配置や立体感にも注意しましょう。
- シンプルなモチーフからスタートする
- 明暗や質感もよく観察する
- 複雑なモチーフに段階的に挑戦する
- 毎日コツコツと描く習慣をつける
描いた作品は時々見返して、自分の成長や課題を確認しましょう。
パースの基礎理解
パースとは遠近法のことで、立体的な空間や奥行きのある構図を描くための重要な考え方です。
まずは一点透視図や二点透視図といった基本パースを理解することから始めましょう。
パースの勉強には下記のようなポイントがあります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 一点透視図 | ひとつの消失点へ向かうパース(室内や廊下など) |
| 二点透視図 | ふたつの消失点を使い、箱や建物などを描く |
| 消失点の設置 | 見ている位置や高さに応じて消失点を調整する |
| 補助線の活用 | ガイド線を利用して正確なパースを引く |
身の回りの風景や身近な空間をパースを意識してスケッチするのも効果的です。
色塗りの基本練習
色彩の勉強は、基本的な色の仕組みと色の組み合わせに慣れることがスタートです。
色相環で似た色や反対の色を理解し、明度や彩度の調整ができると表現の幅が広がります。
まずは好きな作品を模写して色使いを観察してみたり、カラースウォッチを作ったりしましょう。
塗り重ねやグラデーションの練習も重要なポイントです。
最初はベタ塗りから徐々に影やハイライトを追加する手順がおすすめです。
構図の考え方
構図は絵全体の印象を大きく左右する要素で、多くのパターンや黄金比があります。
まずは画面の中で主役を引き立てる配置や、バランスの良い余白のとり方を意識しましょう。
三分割法や対角線構図など、基本的なパターンを参考に完成作品を観察するのも重要です。
- 三分割法で主役を中央からずらす
- 対角線を使って視線を誘導する
- 主役と背景の関係性を考える
- 余白や空間を上手に活かす
自作の下絵でいろんなパターンの構図を試すことで、表現にバリエーションが生まれます。
各分野の参考書や教材
絵の勉強を効率よく進めるには、信頼できる参考書や教材を活用しましょう。
本やネット教材、動画で学べるものも多く、目的やレベルに合わせて選ぶことが大切です。
以下のようなジャンルごとにおすすめの参考書や教材があります。
- デッサン:入門者向けの石膏デッサン練習帳、美術解剖図の本
- パース:パースの基礎が分かる図解書や解説書、透視図法の実践本
- 色彩:カラー理論や配色アイデア集、デジタルイラスト用の色塗り解説書
- 構図:写真集やイラスト構図の参考書、漫画やアニメのレイアウト解説本
口コミやレビューも参考にしながら、自分の目指す表現に近い教材を選んでみてください。
絵の勉強を続けるコツとモチベーション維持法

絵の勉強は継続することが大切ですが、途中でやる気がなくなってしまうことも少なくありません。
ここでは、モチベーションを維持しながら楽しく絵の勉強を続けるコツについてご紹介します。
小さな目標設定
いきなり大きな目標を立てるよりも、小さな目標をいくつも設定するのがおすすめです。
「今日は手を描いてみる」、「一週間で10枚スケッチをする」など、達成しやすい課題を決めると良いでしょう。
小さな成功体験を積み重ねることで、自信につながりやる気も維持しやすくなります。
- 一日一枚でも描くと決める
- 得意なモチーフを決めてみる
- 一ヶ月ごとにテーマを設定する
描く環境の整備
集中して絵を描くためには、自分だけの描きやすい空間を作るのがポイントです。
デスク周りを整理整頓したり、お気に入りの画材を手に取りやすい場所に置くことで気持ちよく作業が始められます。
必要なアイテムをまとめておくことで、描きたくなった時すぐに取り掛かることができるのもメリットです。
| 環境の工夫 | 具体例 |
|---|---|
| 明るさを調整 | デスクライトや自然光を活かす |
| お気に入りグッズ | キャラクター雑貨やモチーフ写真を飾る |
| 作業スペースの確保 | 机まわりを片付けて描きやすく整える |
SNSやコミュニティ活用
一人で勉強を続けるのがつらいときは、同じ趣味を持つ人と交流することで刺激になります。
SNSやオンラインの絵描きコミュニティに参加すれば、作品をシェアする楽しさや仲間からのアドバイスももらえます。
他の人の上達を見て自分も頑張ろうと思えたり、モチベーション維持につながることが多いです。
お気に入り作品の記録
自分が描いた中で気に入った作品や、上手くいったスケッチを写真やファイルにまとめておくのも良い方法です。
時々見返すことで成長を実感でき、やる気の低下を防ぐことにも役立ちます。
また、お気に入りの有名作品や作家の絵をコレクションするのもモチベーションアップにつながります。
成長を感じる工夫
定期的に昔の作品を見直して、どのくらい上達したか比較してみましょう。
上達したポイントに気づいたり、今後の課題も見えるので、より楽しく勉強を続けやすくなります。
自分なりのチェックリストを作って、定期的に振り返るのもおすすめです。
独学と専門講座、どちらを選ぶべきか

絵の勉強には、自分で学ぶ「独学」と、先生やプログラムに沿って学ぶ「専門講座」の2つの方法があります。
自分に合った学び方を選ぶことで、上達のスピードやモチベーションも大きく変わります。
それぞれの特徴を理解して、自分に向いている方法を見つけましょう。
独学のメリット
独学は自分のペースで学習を進められる点が大きな魅力です。
興味を持った分野や描きたいジャンルを自由に選んで、好きなタイミングで勉強することができます。
また、教材費や受講料がかからないため、経済的な負担も少なく始めやすいです。
- 自分の好きな時間に勉強できる
- 好きな教材や題材を自由に選べる
- 費用が抑えられるので気軽にはじめやすい
- 一人で集中して取り組める
独学のデメリット
独学の場合、正しい情報や上達への道筋を自力で見つけなくてはなりません。
間違った描き方を続けてしまうリスクもあり、客観的なアドバイスが得にくいです。
また、モチベーションを保つのが難しく、途中で挫折してしまう場合も少なくありません。
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 間違った知識を覚えてしまう | 書籍や信頼できる動画で学習 |
| モチベーション管理が難しい | SNSなどで同じ趣味の仲間を見つける |
専門講座のメリット
専門講座では、プロの講師から直接指導を受けられるため、正しい描き方やステップを効率的に学べます。
仲間との交流を通じて刺激を受けられるのも魅力の一つです。
悩みや課題をすぐに相談できるので、挫折しにくく、着実に力を伸ばせる環境が整っています。
専門講座のデメリット
専門講座に通う場合、月謝や教材費など経済的な負担がかかることがデメリットです。
また、決まった時間や場所に通う必要があり、生活スタイルによっては続けづらいこともあります。
カリキュラムによっては、自分の描きたい分野を後回しにしなければならない場合もあるので注意しましょう。
絵の勉強に役立つおすすめ書籍・教材

絵の勉強を始める際には、自分に合った書籍や教材を選ぶことが上達の近道です。
初心者から経験者まで幅広く役立つ書籍や教材が多数ありますが、それぞれの分野ごとに特徴や学べる内容が変わってきます。
自分のステップや目的に合うものを選び、効率よくスキルアップを目指しましょう。
基礎本
絵の基礎を身につけるための本は、初心者にとってとても大切です。
線の引き方、形の捉え方、陰影のつけ方など、絵を描くうえで欠かせない基本がわかりやすく解説されています。
はじめて絵にチャレンジする方や、自己流で描いていて基礎を学び直したい方にもおすすめです。
- 「やさしい人物画」(著:A・ルーミス)
- 「はじめてのデッサン」(著:新星出版社編集部)
- 「スケッチの基本」(著:ジョヴァンニ・チヴィルディ)
これらの本は読みやすく、イラストや図解も多いので実践しやすいのが特徴です。
ドローイング本
ドローイング本は、描く力や観察力を高めたい人に適しています。
日々のスケッチやアイデアを形にする練習法が学べます。
短時間で多くの枚数を描くことの重要性も紹介され、表現の幅が広がります。
| 書籍名 | 特徴 |
|---|---|
| 「ドローイングの基本」(著:仲田進二) | 初心者がバランスや構図を学べる |
| 「1日1ページ、365日描く力がつくドローイング練習帳」(著:Liron Yanconsky) | 毎日続けられる構成でやる気が続く |
| 「絵を描くためのドローイング入門」(著:安原成美) | さまざまな画材の技法を網羅 |
継続することで、線や形を捉える直感力が自然と身につきます。
デジタルイラスト本
デジタルイラストを学びたい方には、主にパソコンやタブレットで絵を描くための基本や応用テクニックを学べる本が役立ちます。
人気ソフトウェアの使い方、レイヤーの活用方法、ブラシ設定、キャラクターの描き方など幅広い内容がカバーされています。
色塗りや質感表現など、デジタルならではのテクニックもたくさん紹介されていますので、自分の作風に合った一冊を選んでみましょう。
人体解剖学本
人物イラストやキャラクターを描くなら、人体解剖学の知識がとても大切です。
骨格や筋肉の仕組みを知ることで、より自然で説得力のあるポーズや動きが表現できるようになります。
おすすめの本には、難しい解剖学がイラストとともにやさしく解説されているものが多く、初心者にも取り組みやすいです。
リアルな人物を描きたい方、創作キャラクターの完成度を高めたい方に特におすすめです。
色彩理論本
色彩理論本では、色の基礎的な組み合わせや配色パターン、美しいイラストを作るための法則が学べます。
明度・彩度の使い分けや、色相関図の見方、イラストに調和をもたせるコツがわかりやすくまとめられています。
色の知識を深めることで、作品の印象や世界観を自由にコントロールできるようになります。
はじめて配色に挑戦する方でも、練習しながら楽しく身につけられる内容が充実しています。
絵の勉強でつまずいたときの対処法

絵の勉強を続けていると、誰しも成長が感じづらくなったり、自信をなくしたりする瞬間があります。
つまずきに直面したとき、どう過ごすかはその後の上達にも大きく影響します。
ここでは、よくある悩み別に対処法を紹介します。
モチベーションが落ちた時の行動
モチベーションが下がってしまったときは、無理に頑張ろうとせず気分転換を取り入れましょう。
他の趣味に目を向けたり、お気に入りの画集やイラストを見ることで、改めて「絵が好き」という気持ちを思い出せることがあります。
小さな成功体験も大切です。
- 「今日はペンを持つだけでもOK」とハードルを下げてみる
- 完成度よりも「楽しむ」ことに意識を向ける
- 短時間でできる模写や落書きから再スタートする
他人と比べず、昨日よりも一歩前進した自分を認めてあげましょう。
スランプ時の練習法
スランプに陥ったときは、練習方法を変えることで打開策が見つかる場合があります。
普段あまり描かないモチーフやジャンルに挑戦してみるのも効果的です。
また、「なぜ上手くいかないのか」を分析するのも重要です。
| スランプの要因 | 試してみる練習法 |
|---|---|
| 構図が思いつかない | 写真やイラストの模写で構図を研究する |
| 手が思うように動かない | クロッキーやスケッチの枚数を増やす |
| 色塗りにつまずく | 色彩理論の本を読む、色見本を作る |
悩みを細かく分解し、一つずつ対策してみましょう。
他人との比較を避ける方法
他人の上達具合や作品をSNSなどで見て、落ち込む方は少なくありません。
自分を誰かと比べる癖をやめるには、日々の頑張りや成長を自分自身で認めることが大切です。
おすすめの方法を以下にご紹介します。
- 定期的に自分の過去作品を振り返る
- 1日1つ「できたこと」をノートに書き出す
- SNSを見る時間を意識的に減らす
- 「自分にしか描けない絵」で表現することを目指す
自分だけのペースで成長を感じていくことが、絵の勉強を続けるコツです。
将来の目標や活かし方を描く

これまで絵の勉強に取り組み、さまざまなスキルや表現力を身につけてきました。
ここまで積み重ねてきた経験を、これからどのように活かしていくかを考えることはとても大切です。
例えば、将来的にイラストレーターやデザイナーとして仕事につなげる人もいれば、趣味として自分の作品をSNSで発表したり、他の人と交流を楽しんだりするのも素敵な道のひとつです。
どのような形であっても、自分の目標やビジョンを明確に描いておくことで、学びのモチベーションが高まり、今後の成長にもつながります。
失敗や悩みを経験したことも、あなた自身の力になっています。
この先も絵を通じて、自分らしい表現や夢を広げていきましょう。

