模写がどうしても下手になってしまう理由に悩んでいませんか。
「自分には才能がないのかも」と感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、模写が下手に思える背景には、具体的な原因や行動パターンが隠れています。
本記事では模写が下手になる理由とその解決アプローチを分かりやすく解説し、実践できる対処法や上達のコツまでご紹介します。
模写力を着実に伸ばしたい方は、ぜひ続きをご覧ください。
模写が下手になる理由とその解決アプローチ

模写が思うように描けない、下手だと感じてしまう理由はいくつかあります。これらの要因を理解し、それぞれに合った改善方法を取り入れることが上達の近道です。つまずきやすいポイントを整理し、具体的なアプローチを紹介します。
観察力の不足
模写では、描く対象を正確に観察する力がとても大切です。細かな形や光の当たり方、影の状態など、じっくり観察しないまま描き始めてしまうと、全体のバランスやディテールがずれてしまいます。
観察力を鍛えるためには、まず目を使ってじっくりモチーフを見てみましょう。ただ何気なく眺めるのではなく、「どんな形に見えるか」「どこが一番明るいか」と問いながら観察を重ねるのがおすすめです。
部分ばかり注目して全体を見ていない
模写をするとき、細部ばかりに気を取られてしまいがちですが、作品全体のバランスが崩れる原因となります。
- 大まかなアタリをとる
- 全体像を何度も見返す
- 全体のバランスを優先する
部分を描く前に、大まかな形や構図を紙面にとることが重要です。全体を見渡しながら、細部を詰めていきましょう。
慣れない手の動かし方
筆記具の持ち方や腕の動かし方に慣れていないと、思うような線が引けず、模写がうまくいかないことがあります。
いきなり細かい描写を目指すのではなく、まずは大きくゆったりとした動きで線を引く練習から始めてみてください。慣れてくると、手元のコントロールもしやすくなります。
焦って描くことで丁寧さを欠く
「早く完成させなきゃ」と焦るあまり、雑に線を引いてしまうことがあります。結果として、線や形が乱れたり、思い通りに描けなくなってしまいがちです。
丁寧な作業を心がけましょう。一度描いた線を見直すなど、落ち着いて進めることで作品の出来栄えが大きく変わります。
描く工程の順番を間違えている
模写の際、順序を間違えて描き進めてしまうと、全体のバランスやディテールとの整合性が取れなくなってしまいます。
| よくある描く順番 | 正しい進め方の例 |
|---|---|
| いきなり細部から描きこむ | 全体のアタリ→アウトライン→細部の描き込み |
| 途中で順番を飛ばす | 手順を守り、バランスをチェックしながら進める |
大まかな形を先に描き、その上で細かな部分を描き足していく手順を意識しましょう。
線の引き方の理解不足
線の太さや強弱、滑らかさについて理解が浅いと、模写が不自然に見えてしまうことがあります。線の性質を観察し、どう描かれているかをしっかり真似てみましょう。
練習としては、いろいろな太さや硬さの鉛筆で線の練習をしてみるのがおすすめです。
思い込みによる描写のズレ
自分の中にある「こう見えるはず」という思い込みで描写してしまうと、実際のモチーフと違う部分が生まれてしまいます。
「たしかこんな形だった」ではなく、実際に目の前の対象を観察し、情報をしっかり受け取ることが模写上達のコツです。
模写への苦手意識や自己評価の低さ
自分は模写が苦手だと思い込んでしまうと、チャレンジする意欲が薄れたり、成長を実感しづらくなってしまいます。また、過剰な自己評価の低さも、上達を妨げる要因です。
まずは小さな成功体験を積み重ねて「できた!」という自信をつけていくことが大切です。うまく描けなくても、少しずつ続けていれば必ず前進できます。
模写が下手な人が陥りやすい行動パターン
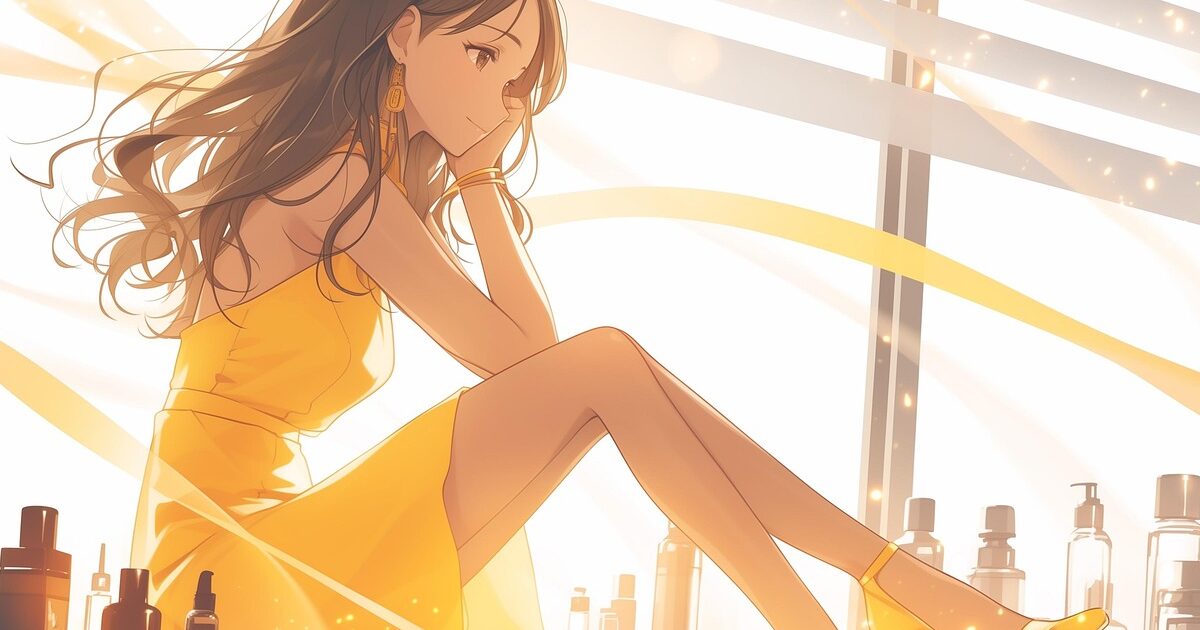
模写が苦手だと感じている人には、いくつか共通する行動パターンがあります。
これらのクセを知って意識的に避けることが、模写上達の近道になります。
見本を見ずに先入観で描く
見本をしっかりと観察せずに、頭の中のイメージだけで描いてしまうことは、模写が苦手な人によくある傾向です。
人は「こんな形だろう」と思い込んで絵を描きがちですが、それが実は見本と大きく違う原因となります。
たとえば、次のような例があります。
- リンゴの輪郭を、おもちゃのような「理想の形」で描いてしまう
- 目や鼻を記号的に表現してしまう
- 形やパーツの位置関係を正しく写さず、自分なりの配置にしてしまう
模写を上達させたいなら、まずは「見本をありのままに観察すること」が大切です。
自分の先入観は一度横に置き、本当に目の前にある形をじっくり見て描く習慣を付けましょう。
模写だけを繰り返してしまう
模写がうまくなりたいからといって、ただひたすら何枚も同じことを繰り返す人がいます。
しかし、やみくもに数をこなしても、大きな上達にはつながりにくい場合があります。
| やりがちな方法 | 上達につながる工夫 |
|---|---|
| 見本をただ真似して描き続ける | 描いた絵と見本を比較して、違いを見つけて修正する |
| 1種類の題材だけにこだわる | いろいろなモチーフを模写する |
| なんとなく描き流してしまう | どこに注意して描いたのかメモする |
大事なのは「どうして似なかったのか」「どの部分が苦手なのか」を振り返ることです。
模写だけで満足せず、分析や反省をすると上達が早まります。
最初から細部にこだわる
全体のバランスを見ずに、最初から細かい部分ばかりを描き込んでしまうのも、模写が下手に感じる一因です。
顔なら目や口、風景画なら木の枝などの一部だけに集中すると、全体のおかしさに気づきにくくなります。
このようなポイントに注意しましょう。
- まずは大きなシルエットや輪郭から形をとる
- バランスを何度も見直しながら進める
- 細部は最後にじっくり描き込む
細かいところを描く前に、全体のアウトラインや構造を意識することで、自然と模写の精度もアップします。
理由別に改善へ導く具体的な対処法

模写が下手に感じる理由は人それぞれ異なりますが、具体的な改善策を試すことで着実にレベルアップが期待できます。
ここでは、観察力や全体把握力など、よくあるつまずきポイントごとに対処法を紹介します。
観察トレーニング
絵を上達させる第一歩は、対象をしっかりと観察することです。
ただなんとなく見るのではなく、輪郭や陰影、細かなディテールに注目してみましょう。
おすすめの観察トレーニング方法は以下の通りです。
- 写真や実物、描きたい対象をじっくり眺め、特徴や形を声に出して説明する
- 1点だけに集中せず、全体→パーツ→全体という視線の動かし方を意識する
- 短い時間で「何が見えているのか」メモに書き出してみる
こうした習慣をつけることで、目の前のものを正確に捉える力が磨かれていきます。
全体のアタリを取る練習
模写が苦手な方の多くは、いきなり細部から描き込み始めてしまいがちです。
まずは全体のバランスや構図を「アタリ」でざっくり取ることが重要です。
このアタリの練習方法には以下のポイントがあります。
- 紙の上で軽く丸・四角・線などでラフに全体像を描き込む
- 大・中・小のパーツに分解してから、細かい部分を描く
- アタリと完成品のズレを後から比較してみる
アタリを正しく描ければ、構図の崩れや違和感も最小限に抑えられます。
シルエット把握練習
物の外側の形=シルエットが曖昧だと、模写の精度も下がってしまいます。
シルエットを把握する練習は、最初に輪郭のみを意識して描くことから始めましょう。
以下の比較表で、シルエット練習の前後で得られる効果をまとめます。
| 練習前 | 練習後 |
|---|---|
| 輪郭線がフワフワして形が不明瞭 | メリハリのある外形になり全体像がとらえやすい |
| 描いているうちに形が崩れてしまう | バランス良く安定したシルエットを描ける |
繰り返し輪郭だけをなぞったり、影絵のように黒ベタで描いてみると、客観的な形の感覚が身につきます。
補助線・グリッドの活用
補助線やグリッドを利用することで、パーツの位置関係や比率が分かりやすくなります。
うまく描けないと感じたら、縦横にガイドとなる線をうっすら入れてから模写しましょう。
ガイドは一時的なものなので、慣れてきたら徐々に減らしていくのがおすすめです。
比率や角度の違和感の原因を視覚的に把握しやすくなります。
描写の工程を分ける練習
一度に完璧な絵を描こうとすると、途中で迷ったり描写にムラが出ることがあります。
以下のように工程を分割し、それぞれステップごとに意識を変えて描くことで安定した模写ができます。
- アタリを入れて全体像を決める
- シルエットやパーツごとの配置を整える
- 細部のディテールや陰影を追加する
- 仕上げや修正を加える
各工程をしっかり分けて反復練習することで、全体と部分のバランスが養われます。
模写力を伸ばす練習方法の選び方

模写力を伸ばしたい場合、自分に合った練習方法を選ぶことが大切です。
やみくもに模写を続けても上達が遅い場合があるので、目的や課題に合わせて工夫しましょう。
いくつかの効果的な練習方法を知り、日々の学習に取り入れることで効率よく力をつけることができます。
「思い出し模写」の導入
ただ原本をなぞるだけでなく、一度見たものを目を閉じて頭の中でイメージし、その後に思い出しながら描く方法が「思い出し模写」です。
この方法を行うことで、観察力や記憶力が同時に鍛えられます。
最初はなかなか思い出せずに曖昧な部分も出てきますが、その都度確認と修正を繰り返すことで、苦手なポイントも意識しやすくなります。
| 一般的な模写 | 思い出し模写 |
|---|---|
| お手本を見ながら忠実に写す | お手本を見た後、イメージだけで描き出す |
| 細部まで再現できるが記憶は残りにくい | 見落としやすい特徴を認識しやすい |
| 繰り返せば模倣は上達する | 分析力・応用力も高まる |
テーマ別反復練習
自分が苦手と感じるモチーフやテーマをピックアップし、それを繰り返し練習することで、効率よく弱点を克服できます。
たとえば人物の手だけ、目だけなど、細かくテーマを絞ることで上達スピードがアップします。
- 人物の顔を連続して描く
- 同じポーズの動物を何度も描く
- 建物のパースだけを集中して反復練習する
テーマ別に集中することで、同じ課題を繰り返し改善でき、成長を実感しやすくなります。
プロセス重視の練習
完成品を重視するよりも、途中のプロセスを大切にする練習も模写上達のポイントです。
どの順番でどの線を描くのか、下書きから仕上げに進む流れにも意識を向けてみましょう。
実際のプロの描き方を観察したり、順序の違いによる仕上がりの変化をまとめてみるのもおすすめです。
| 手順 | 得られる効果 |
|---|---|
| 全体のアタリを最初に描く | バランス良く進められる |
| 細部を最後に描き込む | 主要部分に集中できる |
| 描く順序を色々試す | 自分に合った描き方を発見できる |
このように、ただ写すのではなく、プロセスや順番を研究することで描き方への理解が深まります。
必要以上に「下手」を気にせず描き続けるコツ

模写が思うように上達しないと「自分は下手なんじゃないか」と悩んでしまうことがあります。
しかし、絵のスキルは継続して描くことで少しずつ伸びていくものです。
周囲と比べすぎず、「描き続ける」という気持ちを大切にすることが上達につながります。
ここでは必要以上に自分の「下手さ」にとらわれず、楽しく模写を続けるためのコツについてご紹介します。
自己評価と成長観察
模写を続けていると、どうしても自分の腕前に目がいってしまいがちです。
そんなときは他人と比べる前に、まず自分の過去の作品と比べてみましょう。
数週間前や数か月前に描いた絵と現在の絵を並べてみることで、細かな成長を発見しやすくなります。
また、定期的にスケッチブックなどに自分の模写履歴を残しておくことで、上達が実感しやすくなります。
| 評価ポイント | 成長のサイン |
|---|---|
| 輪郭線 | 以前よりデコボコが減った |
| バランス | モチーフに似ている比率になってきた |
| 陰影 | 立体感が出てきた |
小さな変化も「前進」として評価してみましょう。
小さな成功を振り返る
絵を描いていると失敗ばかりが目についてしまいがちです。
しかし、「今日は目が上手く描けた」「今回は形が似ている」といった小さな成功を見つけて自分を褒めることが大切です。
自信を持って描き続けるためには、成功体験を積み重ねることが大きなモチベーションになります。
- 前回よりも描くスピードが上がった
- 特徴的な部分を再現できた
- 苦手だったパーツが描けた
このように、少しでもできたことに気づいてあげる習慣を大切にしましょう。
他者の模写を観察する
自分の模写と他の人の模写を見比べてみるのも成長のヒントになります。
初心者・中級者・上級者それぞれでどんな違いがあるのか観察し、良い部分を取り入れてみると新しい発見があるはずです。
また、SNSやイラスト投稿サイトなどで「模写過程」や「ビフォーアフター」の投稿も見てみましょう。
| 観察するポイント | 取り入れたい工夫 |
|---|---|
| 線の描き方 | 勢いのある線や、丁寧な下描きの工夫 |
| 形の捉え方 | パーツを簡単な形でブロック分けしている |
| 色の使い方 | 限られた色数で特徴を表現している |
他の人のやり方を観察することで、今まで気づかなかったポイントが見えてくることもあります。
模写が上達すると創作にも生かせる理由

模写が上達すると、ただ上手に描けるようになるだけでなく、その経験が創作活動全体にも大きく役立ちます。
模写を通して得た知識やスキルは、オリジナルのイラストを描く際の基礎となり、自分だけの作品づくりに自信が持てるようになります。
観察力の向上
模写はお手本となる絵や写真をじっくり観察し、細かな部分まで忠実に再現する作業です。
繰り返し模写を行うことで、普段は見逃しがちな形や陰影、質感の微妙な違いにも気づくようになります。
観察力が上がると、自分で想像して描くときも、モデルや風景をしっかりと捉えられるようになります。
- 輪郭線の正確な取り方に気づく
- 陰影や光のあたり方を理解できる
- 細部の個性やニュアンスを見抜ける
このように、観察力の向上は創作のクオリティアップに直結します。
構造の理解力アップ
模写を繰り返すうちに、描きたい対象の構造や成り立ちについて理解が深まります。
例えば人物の場合、骨格や筋肉の配置がどのようになっているのか、どのパーツがどこに付いているのかといった基本的な構造を意識できるようになります。
この理解があると、ポーズや構図を自由にアレンジした創作イラストも自然に描けるようになります。
| 模写の段階 | 理解できること |
|---|---|
| 初級 | 形をなぞるコツ、全体のバランス |
| 中級 | パーツの相互関係、奥行き |
| 上級 | 構造の省略やアレンジ、独自表現 |
構造を理解することで、創作の幅が大きく広がります。
表現の幅が広がる
模写の経験を積むことで、様々な技法や表現方法を自然と身につけることができます。
例えば、筆のタッチや線の引き方、色使いの工夫など、お手本作品から多彩なスタイルを吸収できます。
模写で得た表現技術は、自分のオリジナル作品に応用できるため、作風のバリエーションも増えていきます。
模写を続けるうちに、「こんなふうに描きたい」という想いを形にできるようになります。
これが、創作活動にも大きな自信と強みとなって返ってくるのです。
悩まず行動すれば模写力は着実に伸びる

ここまで模写が上達しない理由やつまずきやすいポイントについて解説してきました。
ですが、どんなに悩んでも、実際に手を動かさない限り模写力は思ったようには伸びません。
大切なのは、失敗や迷いを恐れず、とにかく行動することです。
描き始めたときはうまくいかないと感じても、毎日続けることで少しずつ上達していきます。
理想通りに描けなくても自分を責めず、気楽な気持ちでトライしてみてください。
繰り返し模写を重ねることで客観的に自分の苦手分野も見えてきますし、そこに気づけば改善策も見つかります。
今日の一歩が明日の成長につながります。
模写が下手だと感じていても、継続すれば必ず手応えを感じられるようになるでしょう。
これからも少しずつでも模写の練習を続け、自分のペースで着実にスキルアップを目指していきましょう。


