「絵を描くときに資料を使うのって、ずるいことなのかな?」と悩んだ経験はありませんか。
自分だけでは表現できない部分を補うために参考資料を使うと、周囲の反応やSNSの声が気になり、不安になることもありますよね。
しかし、資料の活用には多くのメリットがあり、その使い方次第で作品の幅や独自性が広がるのも事実です。
この記事では、「絵」と「資料」と「ずるい」というテーマを掘り下げ、気になる心理や正しい資料の使い方、注意点、そしてより良い作品作りに役立つ知識を幅広く紹介します。
資料との向き合い方を知り、自信を持って絵を描くために、ぜひ続きをご覧ください。
絵の資料を使うのはずるい行為なのか

絵を描く際に資料を使うことについて、「ずるい」と感じたり、罪悪感を覚えたりする人は少なくありません。
しかし、資料を活用すること自体は、多くのプロや美術教育の現場で推奨されている方法です。
資料の使い方や、オリジナリティとのバランスが大切なポイントとなります。
「ずるい」と感じる心理的な背景
資料を使うことで、「自分の実力で描いていない」と感じてしまう人は多いものです。
他人と比べて「資料を使わずに描ける人がすごい」と思い、自分を過小評価してしまうこともあります。
また、「資料頼りだと成長しないのでは」といった不安や、盗作と混同してしまう誤解も心理的ハードルの原因です。
資料を利用するメリット
資料を使った絵描きにはさまざまなメリットがあります。
- 正確な形や構造、色味を理解できる
- 自分の引き出しが増え、表現の幅が広がる
- 効率的に短時間でクオリティを上げられる
- 新しいアイデアやインスピレーションを得られる
- プロの現場でも一般的に行われている創作手法である
初心者だけでなく、経験者やプロも頻繁に資料を活用しています。
資料活用とオリジナリティの関係
資料の活用とオリジナリティは両立するものです。
同じ資料を使っても、描く人ごとに完成する絵は異なります。
| 資料の使い方 | オリジナリティへの影響 |
|---|---|
| 構図や要素を参考 | 独自アレンジで個性を出せる |
| 色や質感のみ参考 | 独自キャラクターや世界観に反映しやすい |
| 完全なトレース | オリジナリティは弱くなるが学習法として有効 |
資料を取り入れることで、自分らしさを強調するヒントも得られます。
避けるべき資料の使い方
資料を利用する際、避けたほうがよいケースも存在します。
- 著作権のある他人の作品をそのまま模倣・トレースして公開すること
- 資料画像をそのまま切り貼りして自分の作品と偽ること
- オリジナリティを放棄して資料に完全依存すること
著作権やマナーを守った上での資料活用を心がけましょう。
資料利用への正しい向き合い方
資料は学びと表現力を高めるための大切なツールです。
ただうつすだけでなく、観察し、自分の感性やアイデアを加える意識が大切です。
資料をベースにした練習を繰り返すことで観察眼や応用力が養われ、自分らしい絵が描けるようになります。
成長のための前向きな手段ととらえ、上手に活用しましょう。
プロや上級者の資料活用実例
多くのプロや上級者も、積極的に資料を活用しています。
| 作家 | 資料の活用方法 | 効果 |
|---|---|---|
| イラストレーターA | 自分で写真資料を撮影・収集し、構図やポーズの参考にする | リアルな動きと個性的な表現の両立 |
| 漫画家B | 映画や写真集などから服装や背景、時代考証の情報を集める | 世界観や物語の説得力向上 |
| 画家C | 複数の資料を組み合わせて自分だけのアレンジを加える | 独特な作風や新しい表現スタイルの発見 |
資料を味方につけ、自分の個性や実力を磨くことが、上達やプロへの近道となります。
「絵の資料=ずるい」と感じる主なシチュエーション

絵を描くときに資料を使うことを「ずるい」と感じてしまう場面は意外と多く、特に初心者やネット上ではその意識が強調されがちです。
ここでは具体的にどんなシチュエーションでそのような印象が生まれるのか、ケースごとに見ていきます。
初心者が直面する自己否定
初心者の多くは、絵の上達には「資料を見ずに描くこと」に価値があると思い込みがちです。
そのため、自分が資料を使うと「他の人の努力に頼っている」と感じてしまい、罪悪感や自己否定に陥るケースがあります。
特にSNSなどで「資料なしで描いた」といった投稿を目にすると、自分はずるをしているのでは、と悩むことも少なくありません。
- オリジナリティが損なわれているような気がしてしまう
- 「模写は上達しない」という情報をうのみにしてしまう
- 他の人と比べて自分だけが楽をしているように感じる
SNSやネット上での反応
ネット上では、資料の使い方について意見が分かれやすいのも特徴です。
「資料を使うのは当然」という意見がある一方で、絵の完成度が高い場合などに「資料に頼りすぎ」「ずるい」といった誤解が生まれやすいです。
議論を整理すると、以下のような反応が見られます。
| 反応の種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 肯定的な声 | 「資料をうまく活用できるのも実力」 |
| 否定的な声 | 「完全オリジナルじゃないとダメ」「資料を見てるのはずるい」 |
| 中立的な声 | 「参考にするのは普通だけど、丸写しは避けてほしい」 |
情報発信が活発な分、さまざまな意見を目にしやすいのもSNS特有の現象です。
コンテストや依頼案件の場合
コンテストや依頼案件など、評価や報酬が発生する場面でも「資料=ずるい」と感じる人がいます。
とくに審査基準に「オリジナリティ」を求める場合、資料をどの程度使ったか気にする声があるのも事実です。
ただし、実際には以下のようなポイントを意識している主催者が多いです。
- 資料の使いどころやアレンジ力も評価される
- 「資料参照可」と明記されている場合が多い
- 納期やクオリティが重視され、資料活用は推奨されることも多い
依頼や公募では、資料利用のガイドラインを確認し、適切に活用することが大切です。
資料を活用した効率的な絵の描き方

絵を描く際には、資料をうまく利用することで表現の幅が広がり、より効率的に完成度の高い作品が仕上がります。
資料を見ることは「ずるい」と思われがちですが、実際にはプロのイラストレーターや漫画家も積極的に活用しています。
ここでは資料の活用方法を段階ごとに紹介します。
情報収集のコツ
絵の参考になる資料を集める時は、目的に合わせて情報源を選ぶことが大切です。
例えば、人物の場合はポーズ集や写真素材サイト、風景ならGoogleマップや旅行ブログなどを活用すると効率的です。
信頼できるサイトや書籍から集めることで、描写の正確さも向上します。
- ネット検索でテーマごとに画像を集める
- 写真集や専門書を使って本格的な構造を理解する
- 自分で撮影した写真を活用する
- SNSやイラスト投稿サイトで他の人の作品を参考にする
さまざまな資料を組み合わせることで、独自の表現を追求できます。
アイデア拡張法
資料は単に模写するだけでなく、アイデアを膨らませるヒントにもなります。
同じテーマでも複数の資料を比較することで、新しい発想が生まれやすくなります。
| 資料の種類 | 拡張ポイント |
|---|---|
| 動物写真 | ポーズや表情をアレンジする |
| 映画のワンシーン | 構図やライティングを転用する |
| ファッション誌 | 服装や色の組み合わせを取り入れる |
資料を活用しながら自分らしい要素を加えることで、「オリジナル性」の高いイラストが描けます。
練習での資料の取り入れ方
練習段階でも資料を積極的に使うことで、理解力と観察力が鍛えられます。
最初は模写から始めて、描き慣れるごとにアレンジや省略、異なる資料同士の組み合わせを試してみると良いでしょう。
描いた後は、元の資料と自分の絵を見比べてチェックする習慣もおすすめです。
資料を味方につければ、効率的かつ効果的に絵が上達します。
トレス・模写・参考の違い
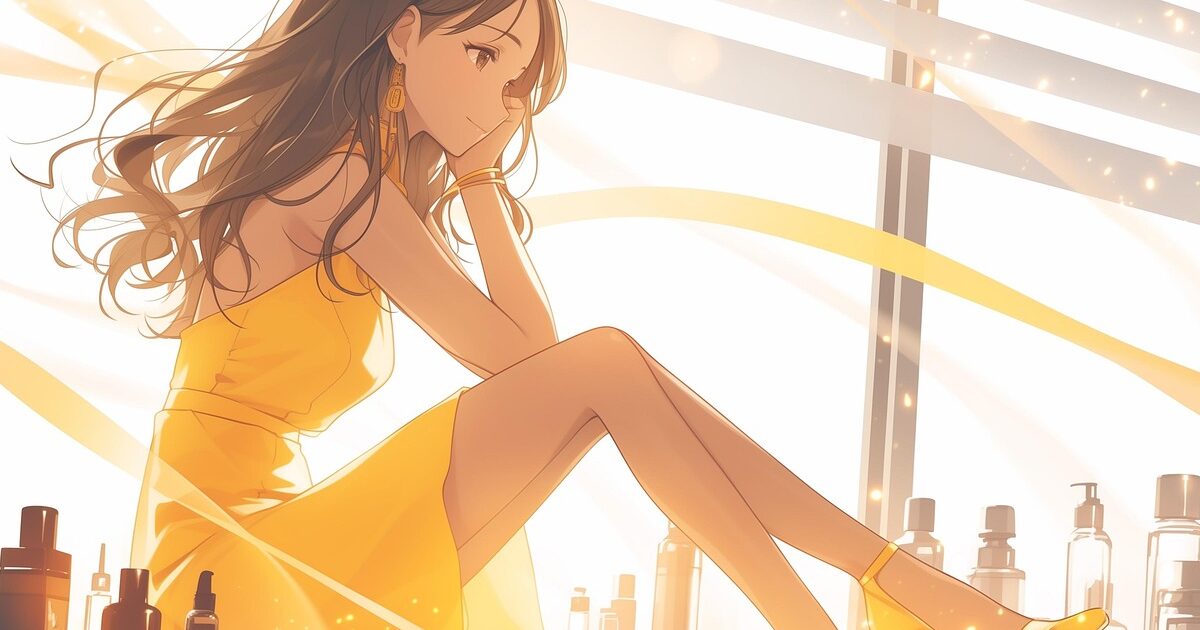
絵を描く際には、資料をどう扱うかが重要なポイントです。
特に「トレス」「模写」「参考」といった言葉は混同されがちですが、それぞれ意味が異なります。
それぞれの言葉の違いをしっかり理解して、資料利用の不安や迷いを解消しましょう。
トレスの定義
トレスとは、既存の画像やイラストの上に紙やレイヤーを重ねて、その線をなぞる行為を指します。
一字一句なぞるので、元の作品と非常に似た仕上がりになるのが特徴です。
練習としては有効ですが、元の画像の著作権を侵害する可能性があります。
特に、なぞった絵を自作として発表したり販売した場合は、トラブルになることがあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 構造やバランスの理解が深まる | 著作権問題が起きやすい |
| 初心者でもすぐ描ける | オリジナリティが出にくい |
模写の定義
模写とは、資料を見ながら自分の手で絵を描き写すことです。
トレスと違い、なぞるのではなく観察して形やバランスを自分で再現します。
自分で手を動かしながら、資料の絵に近づけていくプロセスが重要です。
模写を繰り返すことで、観察力や描写力が鍛えられ、自分の表現にも役立ちます。
- 構図やポーズの理解が深まる
- 自分流のデフォルメやアレンジも可能
- トレスよりもオリジナル性がアップする
参考の範囲
参考とは、資料の一部だけをヒントにしたり、ポーズや雰囲気など要素を取り入れることを指します。
たとえば、手の描き方だけ資料を見て真似する、全体の色使いを参考にする場合もこれに当たります。
参考の範囲であれば、作品全体のオリジナリティを保ちやすく、著作権の問題も比較的起こりにくいです。
ただし、インスピレーション元がはっきりわかるほど似せてしまうと、模写やトレスに近くなってしまうので注意が必要です。
資料を活用しても評価される絵の特徴

絵を描く上で、参考資料を使うことは珍しいことではありません。
しかし、「資料を見て描いた絵はずるい」と思われることもあるのが現実です。
そんな中でも資料をうまく活用しつつ、周囲から高く評価される絵には共通する特徴があります。
ここでは、資料を使いながらもオリジナリティと創意工夫で評価される絵のポイントについて紹介します。
独自表現を加える工夫
資料をそのまま写すのではなく、自分ならではの表現方法を加えることで、絵に個性が生まれます。
例えば筆致の柔らかさや線の強弱、質感の出し方など、資料では得られない“自分の絵らしさ”を盛り込むことが重要です。
以下に独自表現を加えるためのアイデアをまとめました。
- 自分の感情やイメージを反映してデフォルメする
- キャラクターや背景の一部をアレンジしてストーリー性を持たせる
- 光や影の表現を自分流にアレンジする
- 資料にない要素やパーツを新たに加える
こうした工夫を重ねることで、「ただの資料模写」から「創造的な作品」へと仕上げることができます。
構図や色使いのアレンジ
資料を使いながらも、構図や色使いをアレンジすることで、オリジナリティを強く打ち出せます。
同じ資料をベースにしても、配置や視点、色彩を変えるだけでまったく違う印象の作品に仕上がります。
構図や色使いのアレンジ例を表にまとめました。
| アレンジ方法 | 具体的な例 |
|---|---|
| 構図の変更 | 資料の人物の向きを逆にする、背景を広げる |
| 視点の工夫 | ローアングルや俯瞰など、違う視点で描く |
| 色彩のアレンジ | 全体の色味を暖色系や寒色系に統一する |
特に色使いは見る人の印象を左右する大きな要素なので、資料の配色にとらわれすぎず、自分の感性を活かしてみましょう。
資料元が分からないオリジナリティ
資料を使いながらも、どこかで見た画像や構図そのままではなく、見る人が「この元になった資料は何だろう?」と分からなくなるほどのオリジナリティが加わった絵は高く評価されます。
複数の資料を組み合わせたり、自分の経験やイメージから新しい要素を取り入れることで、他にはない作品に仕上がります。
ポイントとして、次のような取り組みが効果的です。
- 複数の資料を組み合わせて描く
- 資料を参考にしつつ全く異なるテーマに仕上げる
- 自身の想像や経験から加筆修正する
こうすることで「ずるい」と言われることなく、自分だけのオリジナリティあふれる絵を描くことができます。
資料を使う絵描きなら知っておきたい著作権リスク

絵を描く際に資料を参考にすることは多くの絵描きにとって重要な工程です。しかし、資料をどのように扱うかによっては思わぬ著作権リスクにつながることもあります。
「資料を使うのはずるい?」と悩む方もいますが、適切な知識を持って資料を活用すれば問題ありません。
ただし、他人が作成した画像やイラストを無断で利用した場合、著作権侵害となる可能性があるため注意が必要です。
特に作品発表やSNS投稿をする場合は、資料の出所や使用範囲についてしっかり意識することが大切です。
フリー素材の基準
絵の資料として活用しやすいのがフリー素材です。けれども、「フリー」とうたわれていても利用にはルールがあります。
フリー素材の中には、商用利用の可否や二次配布、改変など、細かい条件が設定されているものも多いです。利用する前に必ずライセンスを確認しましょう。
代表的なフリー素材サイトで決められている主なルールを以下の表でまとめます。
| 素材サイト名 | 商用利用 | クレジット表記 | 改変 |
|---|---|---|---|
| いらすとや | 可 | 不要(任意) | 可 |
| 写真AC | 可 | 不要 | 可 |
| ぱくたそ | 可 | 不要(推奨) | 可 |
フリー素材であっても違反した利用をすると削除要求やトラブルのもととなります。規約を守って安心して利用しましょう。
トレスと著作権侵害
参考資料をそのままなぞる、いわゆる「トレス」は特に注意が必要です。トレスした絵をSNSに投稿したり、商用利用すると著作権侵害となるケースがあります。
トレスが法律上問題になる主なケースは以下の通りです。
- 元の画像やイラストがはっきり分かるトレス
- 資料画像の構図や線を忠実になぞるだけで、創作性が加わっていない場合
- 著作権者の許可を得ていない場合
自分の練習用でトレスをした場合も、公開する段階では資料の権利や許可をしっかり確認しましょう。安心して絵を発表するためには、一手間かけて元画像との違いを意識することが大切です。
創作絵と資料の安全な線引き
「資料を使って絵を描くのはずるい」という声もありますが、実際には多くの絵描きが資料を活用しています。ただし、どこまでが参考で、どこからが模倣や著作権侵害となるのか線引きが難しいと感じることがあるでしょう。
安全な創作活動のためには、以下のポイントを意識しましょう。
- 1つの画像をそのまま模写しない。
- 複数の資料をミックスして独自の構図やポーズを作る。
- 参考資料はあくまでヒントやインスピレーションとして利用する。
- 独自のアレンジやデフォルメで自分の個性を加える。
また、自分の作品が資料の「複製」とならないためにも、「元の作品と見比べたとき90%以上違いがあるか」「個性や独自性がしっかり表現できているか」を目安にするとよいでしょう。
資料の使い方に悩んだ場合は、元の著作物の権利やガイドラインを確認し、不安な場合は許可を得るなどの対策をしたうえで制作することをおすすめします。
資料を上手く使って絵を描くための前向きな姿勢

ここまで、資料を活用することの良さや、その具体的な方法についてご紹介してきました。
最後に大切なのは、資料を使うことは決して「ずるい」と捉える必要はない、という前向きな気持ちです。
たとえば、プロのイラストレーターや漫画家でも、資料を見ながら描くことは当たり前のことであり、表現の幅を広げるための工夫です。
資料を見ることで、現実味のあるポーズや構造を知り、より正確に、かつ説得力のある絵を描けるようになります。
自分だけで全てを創造しようとせず、必要な知識や情報を素直に取り入れる姿勢こそ、成長や上達の近道です。
「資料に頼るなんて、自分の実力不足では…」と感じることもあるかもしれませんが、それは決して恥ずかしいことではありません。
むしろ、新しい発見や気づきを得るチャンスでもあります。
絵を描く楽しさや表現したい気持ちを大切にしながら、これからも資料を上手に活用して自分の作品づくりに役立ててみてください。
前向きな気持ちで資料と向き合うことで、絵の上達スピードもぐっとアップするはずです。
自分のペースで、絵を描くことを楽しみ続けてください。

