「絵を書きたい」と感じても、いざ始めようとすると何から手を付けていいのか分からず悩んでしまうことはありませんか。
やる気はあるのに、目的や方法が曖昧なままだと、せっかくの気持ちが空回りして途中で挫折してしまうことも少なくありません。
この記事では、絵を書きたいという思いを形にし、楽しく長く続けるためのコツや始め方、練習方法からおすすめ道具までを分かりやすく解説します。
初心者の方でも安心して取り組める内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
絵を書きたいときに最初に知っておきたいこと

絵を書きたい気持ちが芽生えたとき、すぐに画材を手に取るのも楽しいですが、まず基本的な知識や準備をしておくと、よりスムーズに描き始められます。
目的やモチーフ、ジャンルの違いや必要な道具、快適な環境づくり、そして心構えなどを知ることで、絵を描く時間がもっと楽しいものになります。
絵を書く目的の明確化
まず、自分がなぜ絵を書きたいのかを考えてみましょう。
趣味として楽しみたいのか、誰かに見せたりSNSで発信したいのか、または仕事にしたいのかによって、目指す方向が変わってきます。
目的がはっきりしているほど、モチベーションが続きやすくなります。
描きたいモチーフの選び方
初めのうちは、自分が興味を持っているものや好きな物をモチーフに選ぶのがおすすめです。
身の回りの日常的なアイテムやペット、風景など、身近なものから始めることで取り組みやすくなります。
- 好きなキャラクターや動物
- 花や植物などの自然物
- 自分の部屋や街の風景
- 食べ物や雑貨など身近なもの
自身の心が惹かれるものを見つけることで、楽しく描くことができます。
絵のジャンルの違い
絵にはさまざまなジャンルがあります。
自分がどのジャンルに興味があるかを知ることで、参考にする作品や練習方法も変わってきます。
| ジャンル | 特徴 |
|---|---|
| イラスト | 漫画やアニメ風などカジュアルな描写が特徴 |
| デッサン | 陰影や形を正確に表現する練習向き |
| 水彩画 | 透明感のあるやさしい色合いが楽しめる |
| 油絵 | 重厚感や質感表現に優れる |
| デジタルアート | パソコンやタブレットで制作する絵 |
気になるジャンルを試してみるのも良い方法です。
必要な道具の準備
絵を書くための道具は、選ぶジャンルやスタイルによって異なります。
紙と鉛筆だけでも始められますが、水彩画なら絵の具や筆、デジタルアートならタブレットや専用ソフトが必要です。
最初は最低限の道具から揃えて、徐々に買い足していくと無理なく続けられます。
環境づくりのポイント
快適に絵を書くためには、明るい場所や十分なスペースを確保することが大切です。
整理整頓された机の上だと道具も使いやすく、集中しやすくなります。
また、長時間座っても疲れにくい椅子や、コピー用紙やクロッキー帳などの予備もあると安心です。
心構えと挫折しない工夫
絵はすぐに上達しなくても大丈夫です。
時には思い通りに描けなかったり、モチベーションが下がることもあります。
そんなときには、以下のポイントを意識すると続けやすくなります。
- 上手な人と自分を比べすぎない
- 小さな進歩を自分で認める
- 描ける日だけ描く、無理に毎日続けなくてもOK
- 時にはお気に入りの作品だけを見直す
- 描くことそのものを楽しむ気持ちを持つ
自分なりのペースで取り組むことが、長く楽しく続けるコツです。
絵を書きたい人におすすめの練習方法

絵を書きたいと思ったとき、日々の練習方法を工夫することで、より効率的に上達することができます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、楽しみながら取り組むことが大切です。
さまざまな練習方法を試し、自分に合ったやり方を見つけてみてください。
模写の練習
模写は好きなイラストや写真を見ながら、そっくりそのまま描いてみる練習です。
プロのイラストや有名な作品を模写することで、線の描き方や構図、バランスの取り方など自然と学ぶことができます。
最初は簡単なイラストや身近なキャラクターから始めてみましょう。
模写を繰り返すことで、表現力や観察力が身に付きます。
- 自分のお気に入りのイラストを選ぶ
- 線の太さや陰影もしっかり観察する
- 何度も描き直してみる
クロッキーの基礎
クロッキーは短い時間で対象をざっくりと描き取る練習方法です。
人や動物の動き、全体のバランスを捉える力が身に付きます。
5分など短時間で描くことで、細部にこだわらず、大まかな形や流れをつかむトレーニングになります。
普段からスケッチブックを持ち歩いて、身の回りのものを素早く描くことを心がけましょう。
| クロッキーで練習する対象 | 得られる効果 |
|---|---|
| 人のポーズ | バランス感覚の向上 |
| 動物 | 動きや表情の観察力アップ |
| 身近な小物 | 形を捉える力が付く |
トレースの活用
トレースは好きなイラストや写真の上から紙を重ねて、輪郭などをなぞって描く練習方法です。
線の流れや形を手でなぞることで、自然な線やバランス感覚を身につけることができます。
手の動きを覚えたいときや、どうしても崩れてしまうパーツの練習におすすめです。
トレースだけでなく、慣れてきたら自分の力で描く練習も取り入れてみましょう。
パーツごとの描き分け練習
顔や手、足、髪型など、個々のパーツに分けて練習することで、それぞれの特徴を理解しやすくなります。
パーツごとに何度も描いてみて、苦手な部分を重点的に練習すると効果的です。
参考書やオンラインで公開されている描き方講座を参考にしながら、形や角度のパターンを増やしていくこともポイントです。
部分練習を重ねることで、全体を組み合わせたときのバランスもぐっと良くなります。
オリジナルイラストへの挑戦
基礎練習に慣れてきたら、いよいよ自分だけのオリジナルイラストに挑戦してみましょう。
頭の中にあるアイデアや物語を自由に表現することで、創造力や構成力がどんどん磨かれます。
最初はうまく描けなくても気にせず、自分が楽しいと思えるテーマで描いてみることが大切です。
新しい発見や自分なりの表現が増えて、絵を書くことがますます楽しくなります。
絵を書きたい人が意識したい上達のコツ

絵を書きたいけれど、なかなか思うように上達できないと感じることもあるでしょう。
上達するためには日々の練習だけでなく、意識したいコツがいくつかあります。
ここでは、絵を書く人が押さえておきたいポイントを紹介します。
観察力の強化
絵を上手に描くためには、対象をよく観察する力が大切です。
ただ何となく見るのではなく、形や陰影、色の違いに意識を向けてみましょう。
たとえば身の回りの物をじっくり見たり、写真や実物と自分の絵を比べたりすることで観察眼が養われます。
- 写真を見ながら描いてみる
- 本物の花や果物を観察してスケッチする
- お手本と自分の作品を見比べて違いを探す
細かな違いに気付けるようになると、自然と絵のクオリティも上がります。
描き直しを恐れない姿勢
失敗を恐れて描く手が止まってしまうこともありますが、どんどん描き直すことは重要です。
最初から完璧に描こうとせず、間違えたら修正していくくらいの気持ちで描くと緊張せずに進められます。
何度も繰り返し描くことで、表現したいイメージに近づけることができます。
| 描き直しの例 | ポイント |
|---|---|
| 輪郭線を何度も描き直す | 自分が納得いく形になるまで修正OK |
| 色を重ねて調整する | 思い通りの色味になるまで根気よく試す |
失敗や変化を楽しめると、継続しやすくなります。
自分の作品の振り返り
描いた絵は見返して振り返ることが大切です。
完成したらしばらく時間を置いてから改めて見ると、良い部分や改善したい点も発見しやすくなります。
毎回振り返ることで、自分の成長や得意・不得意を意識できるようになります。
ノートやスマホなどに絵を記録しておくのもおすすめです。
気軽にメモして「ここが良かった」「この部分はもっとこうしたかった」と感想を書き残しておくと次回に活かせます。
他人からのアドバイスの受け方
他の人から意見やアドバイスをもらう機会もあるでしょう。
アドバイスを素直に受け止めることは、上達につながります。
ただし、自分の考えや大切にしたい部分も無理に曲げる必要はありません。
参考になる意見は前向きに取り入れ、自分には合わないと感じたものは無理せず流して大丈夫です。
感謝の気持ちを持って聞くことで、人との交流も深まります。
絵を書きたい人向けのおすすめ道具と選び方

絵を書きたいと感じたときには、まずどんな道具を選ぶかが大切です。
初めての人も慣れている人も、自分に合ったアイテムを使うことで、絵を描く楽しさや表現の幅が広がります。
ここでは紙やスケッチブック、鉛筆・ペン、デジタル機材、カラー画材の選び方と特徴を紹介します。
紙・スケッチブックの種類
紙やスケッチブックは、描く絵や使う画材によって使い分けると描きやすさが変わります。
ざらざらした紙は鉛筆や木炭に向いていて、細い線をしっかり引けます。
つるつるした紙はペンやマーカー、水彩にもぴったりです。
スケッチブックには糸綴じ、リング製本などがあります。
持ち運びしやすいA4サイズや、ノート型のミニサイズも人気です。
- 画材に合った紙を選ぶ
- 外出先で描くなら軽量タイプ
- 大きな作品にチャレンジしたい場合は大判サイズ
自分の描くスタイルや作品イメージに合ったものを選びましょう。
鉛筆・ペンの特徴
鉛筆には濃さを示す「H」「B」などの種類があります。
Hは硬くて薄い線、Bは柔らかくて濃い線が描けます。
初めての方はHBかBがおすすめです。
ペンは線の強弱や滑らかさが重要です。
ボールペン、ミリペン、筆ペンなど選択肢も豊富です。
| 道具 | 特徴 | おすすめ用途 |
|---|---|---|
| 鉛筆 | 消せる・陰影表現が得意 | 下書き・デッサン |
| ミリペン | 均一な細い線が描ける | マンガ・イラスト線画 |
| 筆ペン | 線の強弱や雰囲気が出せる | イラスト・書道 |
自分の表現したい雰囲気に合わせて、いろいろ試してみるのもおすすめです。
デジタル機材の選び方
近年はデジタルで絵を書く人も増えています。
パソコンやタブレット、ペンタブレットが主な機材です。
まずは手になじむサイズや重さを重視しましょう。
予算や目的によって、選ぶ機材が変わります。
- 初心者はタブレット+スタイラスペンが使いやすい
- 細かい作業や高画質なら液晶ペンタブレット
- 持ち運び重視ならiPadなどの軽量タイプ
- デジタルソフトの互換性も確認する
自分の使いたいアプリや環境、描くスタイルをよく考えて選びましょう。
カラー画材の使い分け
色を使って絵を描く場合、どんな画材を使うかで仕上がりの印象が大きく変わります。
色鉛筆はやさしい風合いが出せますし、水彩絵の具は透明感やにじみが特徴です。
マーカーはしっかり発色し、均一な面を塗るのに向いています。
アクリル絵の具は重ね塗りができて、厚みのある表現にも使えます。
迷ったら少量セットで試しに使ってみるのも良い方法です。
自分が思い描く表現や作品に合ったカラー画材を見つけてみましょう。
絵を書きたい気持ちを継続させるための方法

絵を書きたいと思っても、続けるのが難しいと感じることは少なくありません。
その気持ちを継続させるには、毎日のちょっとした工夫が大切です。
すぐに成果を求めず、少しずつ描く習慣を身につけることで、自然と楽しく絵を書き続けられるようになります。
絵を書く仲間と交流を持つことも、もう一つのポイントです。
習慣化のコツ
絵を書くことを習慣にするためには、日常生活の中に自然に組み込む工夫が効果的です。
例えば、朝のコーヒータイムや寝る前のリラックスタイムに、5分だけでも絵を描く時間を設けてみましょう。
また、決まったノートやスケッチブックを用意し、そこに毎日少しずつ書き足していくのもおすすめです。
- タイマーを使って短時間でも作業する
- 「○日連続達成」など小さな目標を設定する
- 描いた絵をカレンダーやSNSに記録する
少しずつでも続けることで、描くこと自体が習慣に変わっていきます。
モチベーション維持方法
絵を書きたいという気持ちは、時には下がってしまうこともあります。
そんなときは、自分なりの工夫でモチベーション維持を図りましょう。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 目標を立てる | 「週に3枚描く」など無理のない目標を設定 |
| お気に入りの画材を使う | 気分が上がる文房具やツールを取り入れる |
| 描きたいものリストを作る | アイデアが浮かびやすく、迷った時も安心 |
| 他の人の作品を見る | 刺激をもらってやる気をチャージ |
自分に合った方法を見つけることで、長くモチベーションを保つことができます。
コミュニティとの交流
同じく絵を書きたい仲間との交流は、刺激や励みになります。
SNSやオンラインコミュニティ、地元のワークショップなどで、気軽に作品をシェアしたりコメントしあうことで成長や継続につながります。
またフィードバックをもらうことで新しい発見や目標も生まれやすくなります。
もし機会があれば、オフラインで集まって一緒に描いたり作品展を開くのも良い方法です。
人とつながることで、絵を書く楽しさをより感じられるでしょう。
自分なりの表現を見つけたいときのアプローチ

絵を書きたいと感じるとき、自分らしさや独自の表現を持ちたいと思う人は多いものです。
しかし、最初からオリジナリティにこだわり過ぎてしまうと、逆に手が止まってしまうこともあります。
自分なりの表現を見つけるには、いろいろな方法を試しながら自分に合った道を探っていくことが大切です。
ここでは、実際に効果的なアプローチをいくつか紹介します。
好きな作家・作品の研究
まず、自分が心から「良い」と思える作家や作品をじっくり観察しましょう。
なぜ惹かれるのか、どんな構図や色づかい、表現の仕方が好きなのかを自分なりに分析してみることが大切です。
- 一部分を模写してみる
- 作家のインタビューや制作過程を調べる
- 好きな作品の共通点をノートに書き出す
このように研究を重ねることで、自分が「本当に描きたいもの」や「表現したい雰囲気」が見えてくることがあります。
また、尊敬する作家の手法を自分なりに取り入れることで、自分だけのオリジナル表現が徐々に形成されていきます。
複数の画材の試用
画材によって作品の雰囲気や描きやすさは大きく変わります。
ひとつの画材に絞らず、様々な種類を試してみることも表現の幅を広げる方法です。
| 画材の種類 | 特徴 | おすすめポイント |
|---|---|---|
| 鉛筆・色鉛筆 | 線が表現しやすく、細かい描写に向いている | 初心者でも扱いやすく、修正しやすい |
| 水彩絵の具 | 透明感やにじみを活かした柔らかい表現が可能 | 広い面の色付けや幻想的な作品作りに最適 |
| アクリル絵の具 | 発色が良く速乾性が高い | 重ね塗りや大胆な色表現に向いている |
いろんな画材を使ってみるうちに「この質感が好き」「この道具は自分に合っている」といった発見があり、より自分らしい表現に近づくことができます。
自分の感性を信じる方法
誰かと比べてしまうことで自信を失いやすいのが絵の世界の難しさです。
自分の感性を信じるためには、まず自分自身の感じたことや好きな世界観を大切にする意識が重要です。
もし失敗したと思っても、その経験こそが自分の引き出しを増やすヒントになります。
日記やスケッチブックに「今日描いてみてどう感じたか」「どんな表現が気に入ったか」などを記録してみましょう。
積み重ねていくうちに、少しずつでも自分なりの自信が育っていきます。
表現は自由であり、上手い・下手ではなく「自分が楽しい」と思えることが一番大切です。
絵を書きたい気持ちを行動に移したいあなたへ
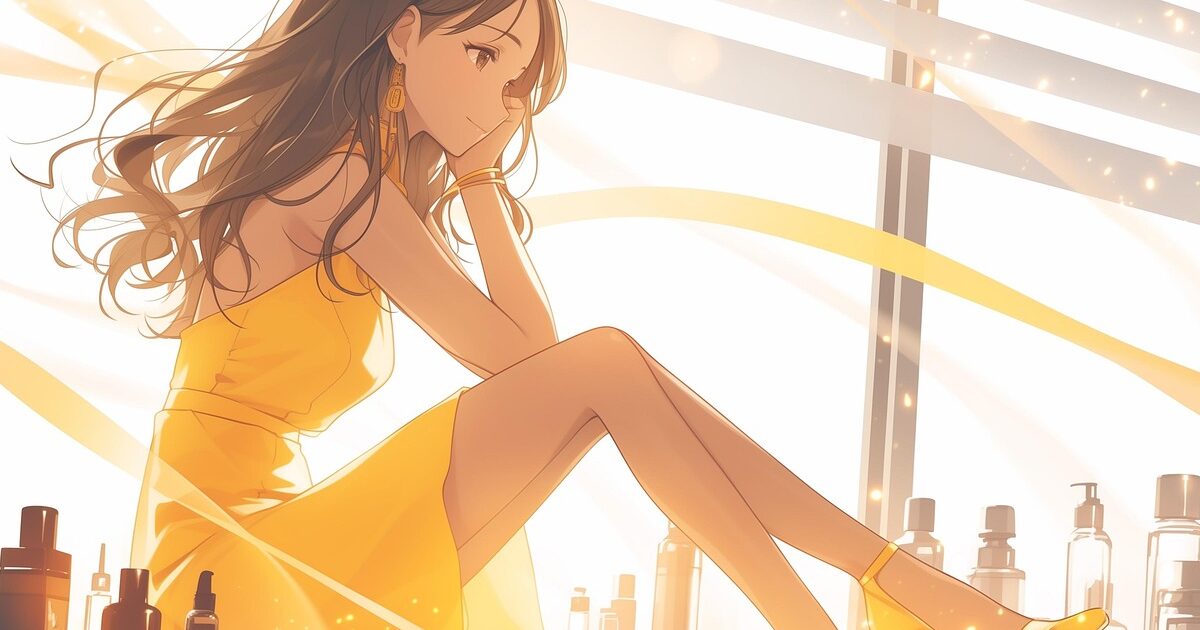
ここまで絵を描くための基礎や続けるコツなどを紹介してきました。
今、あなたの中に芽生えた「絵を書きたい」という気持ちはとても大切なものです。
描き始めるタイミングに遅いも早いもありません。
一歩踏み出すことで、あなたの世界はきっと広がります。
最初はうまく描けなくても大丈夫です。
描いた分だけ少しずつ自分らしい表現が見えてきます。
今日のわずかな時間でも、紙とペンがあれば絵を始められます。
失敗を恐れず、まずは手を動かしてみてください。
これからも絵を描く楽しさや成長を感じながら、あなただけの作品を生み出していきましょう。
あなたの「描きたい」気持ちが、素敵な創作の第一歩になりますように。


